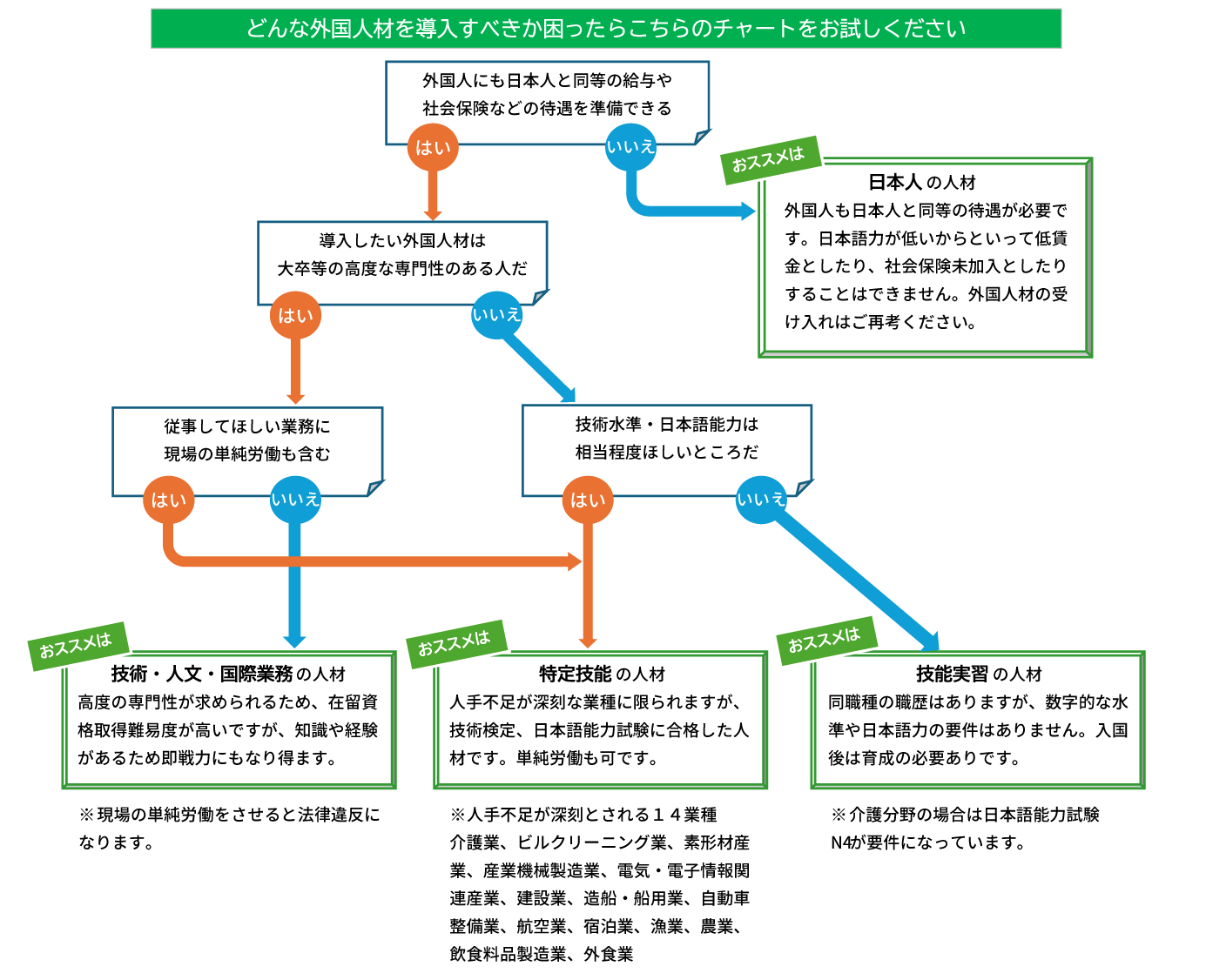外国人受け入れに関するワンストップサービスを提供します!
外国人を雇用するということが珍しくなくなってきた昨今。人手不足等のため外国人雇用を進める企業も増えて来ています。ただ、実際にいざ雇用しようとしても、いったいどんな手続きをしたら良いのかまったく見当もつかない、ということも多いと思います。
今までは第1次産業においては技能実習生の受け入れが一つの大きなセオリーでしたが、2027年頃を目途に技能実習制度を廃止し、育成と長期就労を目指した新たな外国人雇用制度がスタートすることが決まっています。では、どのように外国人を雇用すればよいのか、雇用したとして労務管理はどうしたらよいのか、頭を悩ませる方にワンストップのサービスを提供いたします。
今までは第1次産業においては技能実習生の受け入れが一つの大きなセオリーでしたが、2027年頃を目途に技能実習制度を廃止し、育成と長期就労を目指した新たな外国人雇用制度がスタートすることが決まっています。では、どのように外国人を雇用すればよいのか、雇用したとして労務管理はどうしたらよいのか、頭を悩ませる方にワンストップのサービスを提供いたします。
特に、技能実習制度に代わる外国人労働者受入制度として近年増加している特定技能制度に関しては、当法人を登録支援機関としてご活用していただくことが可能です。登録支援機関は、特定技能資格で入国・就労する外国人の入国時の空港送迎や行政手続きの付き添い、勤務開始後の定期的な面談等のサポートを受入企業に代わって行うことできます。
当法人は、入国管理業務に精通した申請取次行政書士と労務管理の専門家である社会保険労務士が在籍しておりますので、外国人受け入れに関して入国前のビザ申請から始まり、入社時の社会保険の適用、労務管理、在留資格更新に至るまで幅広く対応しております。
※申請取次行政書士とは
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められています。
主な在留資格の比較表
技術・人文・国際業務
特定技能1号
技能実習生
業務内容
IT、医療、教育、法律、通訳などの専門分野の業務のみ。単純作業がメインの業務では雇用できない。
特に人手不足が深刻とされた業種のみ対象。メイン業務に附帯するものであれば単純作業も可。
建設、食品製造、遷移、機械金属など多くの職種・作業の中から1つを指定。例えば畜産なら養豚なのか養鶏なのか酪農なのか、という作業の区別がある。
在留期間
最長5年。更新すれば延長可能。
通算最長5年。
2号に移行すれば更新にて延長可能。
2号に移行すれば更新にて延長可能。
1号:1年 2号:2年 3号:2年
最長で合計5年
※3号移行できない業種あり
最長で合計5年
※3号移行できない業種あり
学歴・技能試験
大学卒または専門学校卒
または実務経験10年以上
または実務経験10年以上
産業ごとの技能検定合格
日本語能力試験N4以上
日本語能力試験N4以上
同種の業務に従事した経験等があること
介護は日本語能力試験N4以上
介護は日本語能力試験N4以上
受入方法
自社の求人でも可能
自社の求人でも可能
登録支援機関からの紹介による
有料職業紹介会社よりの紹介による 等
登録支援機関からの紹介による
有料職業紹介会社よりの紹介による 等
監理団体からの紹介による
送り出し機関からの紹介による
送り出し機関からの紹介による
業種
【技術】システムエンジニア、プログラマー等
【人文】コンサルタント、商品開発者、弁護士、税理士等
【国際業務】翻訳・通訳、語学講師、デザイナー等
多岐にわたる
【人文】コンサルタント、商品開発者、弁護士、税理士等
【国際業務】翻訳・通訳、語学講師、デザイナー等
多岐にわたる
全部で14種の業種で受入可能。
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業
86職種158作業が1号、2号対象となっている。3号に移行できない職種・作業もある。
受け入れ可能人数
制限なし
介護業、建設業以外では制限なし
建設業:常勤職員の総数を超えないこと
介護:日本人等常勤介護職員の総数を上限
建設業:常勤職員の総数を超えないこと
介護:日本人等常勤介護職員の総数を上限
1号:常勤職員の総数と同数まで
2号:常勤職員の総数の2倍
3号:常勤職員の総数の3倍
2号:常勤職員の総数の2倍
3号:常勤職員の総数の3倍
転職
在留資格の範囲内であれば可能
同じ業種であれば可能
転職はできない。1年経過後は一定条件で転籍(実習先の変更)できる。
メリット
高度な専門性をもった人材を安定して長く雇用することができる。
技術検定合格者なので、企業が必要とする技術を持った人材を確保できるため人手不足の解消になる。
2号へ移行できれば永続的に雇用できるため、技術の承継も期待できる。
2号へ移行できれば永続的に雇用できるため、技術の承継も期待できる。
技能実習生は目的意識を持って素直に真面目に取り組む人が多いため、社内の意識レベルの向上につながります。
帰国してからも、日本の文化や社会に理解のある人材として祖国と日本の架け橋になってくれることが期待できます。
帰国してからも、日本の文化や社会に理解のある人材として祖国と日本の架け橋になってくれることが期待できます。
デメリット
在留資格の更新があるため、在留期間の管理を徹底する必要がある。
転職が可能なので、日本人社員と同様に公正な待遇や評価などが必要。
転職が可能なので、日本人社員と同様に公正な待遇や評価などが必要。
建設業であればJAC(特定技能外国人受入事業実施法人)への加入が義務付けられているため、継続的に費用がかかる。
入国後も本人の日本語習得や地域交流などのサポートが継続的にされている必要がある。
入国後も本人の日本語習得や地域交流などのサポートが継続的にされている必要がある。
基本的に監理団体を通じて受け入れることがほとんどのため、監理団体への費用が掛かる。
受入手続きや制度が複雑で煩雑である。
住居の提供や細かな実習計画・日誌等の作成、各種社会保険の完備が必要。
帰国することが目的のため長期雇用できない。
受入手続きや制度が複雑で煩雑である。
住居の提供や細かな実習計画・日誌等の作成、各種社会保険の完備が必要。
帰国することが目的のため長期雇用できない。
その他
従事する仕事は学歴または職歴と関連性のある職務でなければならない。
日本国内における深刻な人手不足を解消するために設けられた制度のため、人材確保が目的。
日本の優れた技術や知識などを習得し、それを母国に持ち帰って役立ててもらうことを目的とした国際貢献が目的。労働力の確保が目的ではない点に注意。
よくある質問
FAQ
外国人労働者に働いてもらうにはどんな在留資格がありますか?
いわゆる就労ビザには多くの種類があります。それぞれのビザによって国内で従事できる仕事や業種、職種が細かく指定されており、範囲外の仕事をすると法律違反となります。最も多いのは技術・人文・国際業務ビザで就労する人で、全体の7割と言われています。今後は、特定技能のビザで就労する人が多くなると見込まれています。
外国人労働者は何年くらい働けるのでしょうか?
在留資格の種類によっても在留できる期間は異なります。最初は短めの在留が許可され、在留資格更新のたびに信頼関係を増すことにより在留期間が長くなります。通常は最初の1回目の申請(新規申請)の場合は1年のことが多いように見受けられます。在留中に税や保険料の滞納、交通違反等がないか等生活態度ももちろん審査の対象となります。
技能実習制度と特定技能制度はどんな違いがありますか?
技能実習制度は日本の優れた産業技術を途上国などに移譲するための制度で、国際貢献が主目的です。一定期間で日本の技術を身に着けたあとは帰国が必要です。
対して特定技能制度は、ある程度の高い技能を持った外国人を即戦力として日本で就業させることができる制度で、慢性的な人手不足を補う目的があります。
対して特定技能制度は、ある程度の高い技能を持った外国人を即戦力として日本で就業させることができる制度で、慢性的な人手不足を補う目的があります。
在留資格の申請を会社でやろうと思うのですが可能でしょうか?
在留資格申請の経験がない人でも申請することは可能です。ただ、ウェブなどで公表されている書類の他にも審査に必要とされるものは多くありますので、不足書類の指摘を山ほどされることになり、時間と労力を相当程度かけることになります。
外国人を雇用するときに外国人労働者にはどんな配慮が必要ですか?
外国人労働者は日本語が発展途上で社会生活のルールが母国と異なることもあるため、仕事上も生活上も各種のギャップに悩みます。悩みが大きくなる前に密なコミュニケーションをとり、不満の芽を積んでいくような細かなサポートが必要です。
外国人を雇用するときにいま雇用している日本人労働者にはどんな配慮が必要ですか?
受け入れる日本人側には、同じ仕事をする対等な仲間であるという意識を持ってもらうことが大前提です。国籍などで差別しない、させない環境づくりが大事です。
日本語能力が低いことを理由に、外国人の給与を低くしても良いでしょうか?
外国人労働者でも労働内容が同じであれば日本人労働者と同等の待遇が必要です。
外国人でも社会保険等は加入させなければならないのでしょうか?
外国人労働者であっても、日本人労働者と同様に社会保険(労災・雇用保険、健康保険、厚生年金)の適用が必要です。永住しない外国人に年金の支払いは不要と考える方もいますが、退職して帰国する場合は要件を満たせば一時金の支給を受けられますので保険料がすべて無駄になるわけではありません。
登録支援機関とは何ですか?
登録支援機関とは外務省に登録された機関で、外国人を受け入れた企業等の委託により、特定技能制度により入国してくる外国人労働者がスムーズに仕事に取り掛かれるように入国から帰国まで各種支援活動を行います。
登録支援機関にはどんなことをしてもらえますか?
入国前の事前ガイダンス、出入国の際の送迎、携帯電話や銀行口座等の開設、日本生活のルールに関するオリエンテーションの実施、公的手続きへの同行といった就業時のサポートの他に、職場や生活の相談対応、日本人との交流促進などの就業中のサポートなど多岐にわたります。受入企業と相談の上、必要なサポートを選択していただきます。